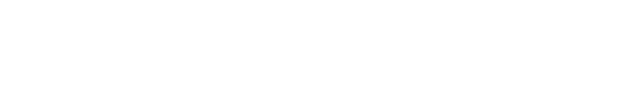「貧血」とは──日常会話と医療現場のギャップ
「最近なんだか立ちくらみがする…もしかして貧血かも?」
そんなふうに感じたこと、一度はあるのではないでしょうか。
でも実は、日常会話で使われる「貧血」と、医療現場での「貧血」には少しギャップがあります。
医療現場での「貧血」とは?
医学的に「貧血」とは、赤血球の中に含まれるヘモグロビンの濃度が、基準より少ない状態を指します。
つまり、酸素を全身に届ける“輸送役”である赤血球の機能が足りない状態なのです。
赤血球は酸素を運ぶ“トラック”のようなもので、その中に積まれている「荷物」がヘモグロビン。
このヘモグロビンが酸素と結びついて、体のすみずみに酸素を届けています。
血液には3つの主役がいる
血液中には、主に以下の3つの細胞が含まれています:
-
赤血球:酸素を運ぶ
-
白血球:体を守る(免疫担当)
-
血小板:出血を止める(止血作用)
このうち、赤血球の中のヘモグロビンが減っている状態が「貧血」です。白血球や血小板が正常でも、貧血は起きます。
「赤血球が足りない」にも種類がある?
貧血と診断されたとき、重要になるのが、赤血球の「大きさ(MCV)」などの情報を確認することです。
赤血球の大きさは、貧血のタイプや原因を探る重要なヒントになります。
主な3タイプの貧血:
-
小球性貧血:赤血球が小さい
→ 鉄欠乏性貧血に多い。 -
正球性貧血:赤血球の大きさは正常
→ 慢性疾患や出血などが原因のことも。 -
大球性貧血:赤血球が大きい
→ ビタミンB12や葉酸の不足の可能性があります。
また、慢性的なアルコール摂取でも見られることがあります。
まとめ:ただの“息切れ”ではない、赤血球からのサインかも
-
✅ 「貧血」とは、赤血球の中のヘモグロビンが不足した状態
-
✅ 白血球や血小板が正常でも、貧血は起こる
-
✅ 赤血球の「大きさ」から、貧血の原因が見えてくることがある
「疲れやすい」「息切れがする」──
そんなサインを軽く見過ごさず、血液検査という“見える化”を活用してみてください。
体調不良の背景には、“赤血球の声”が隠れているかもしれません。